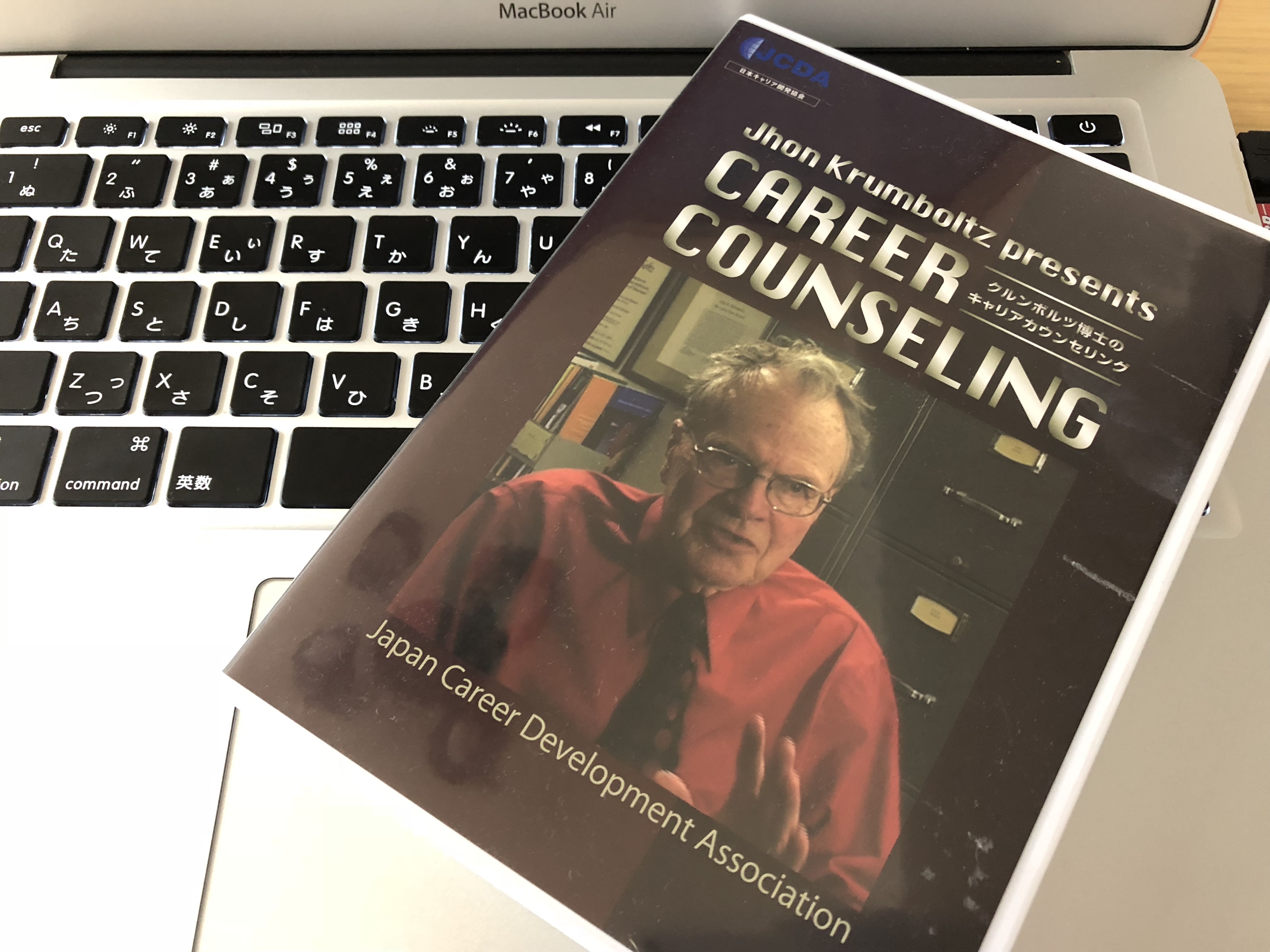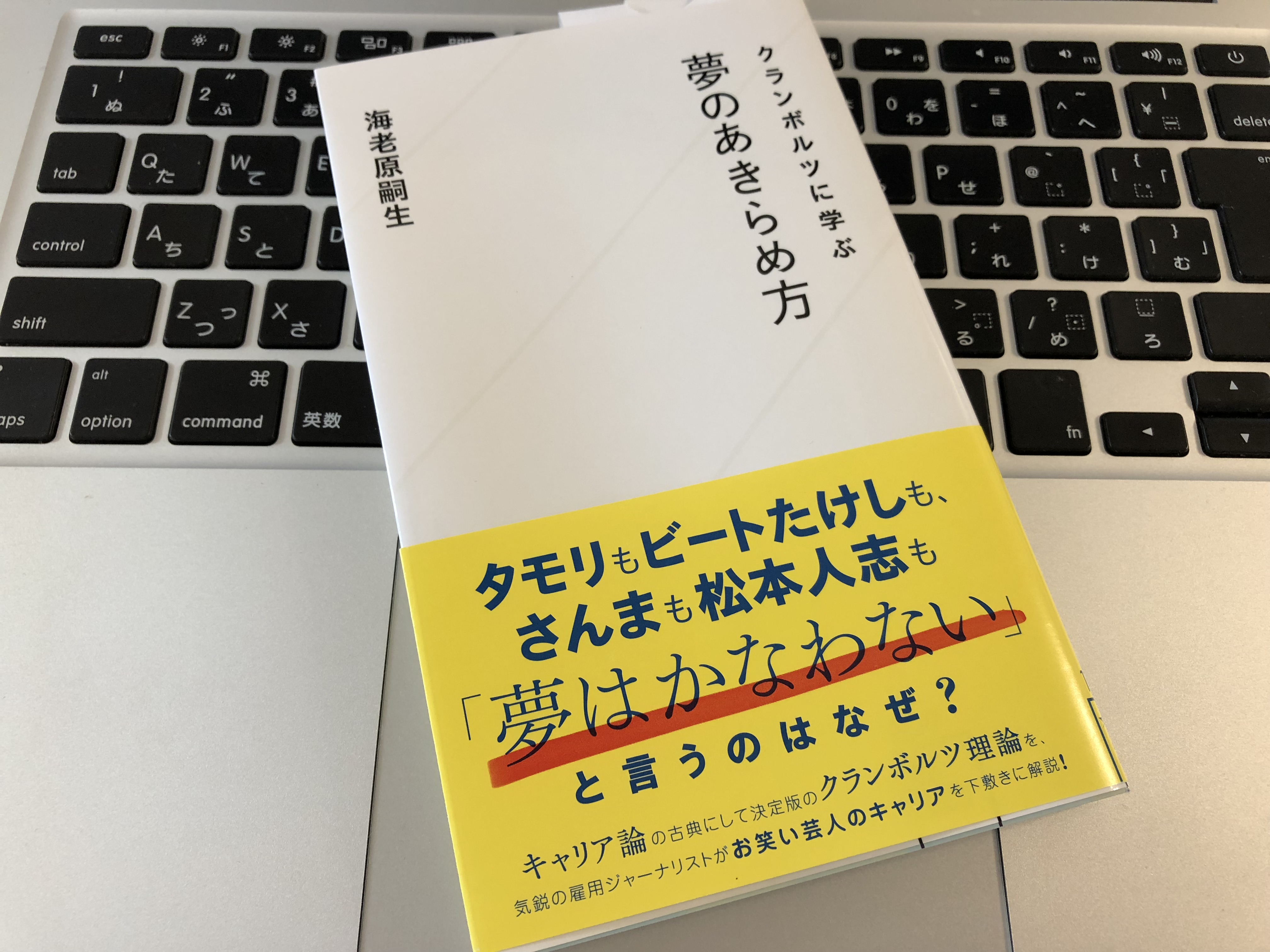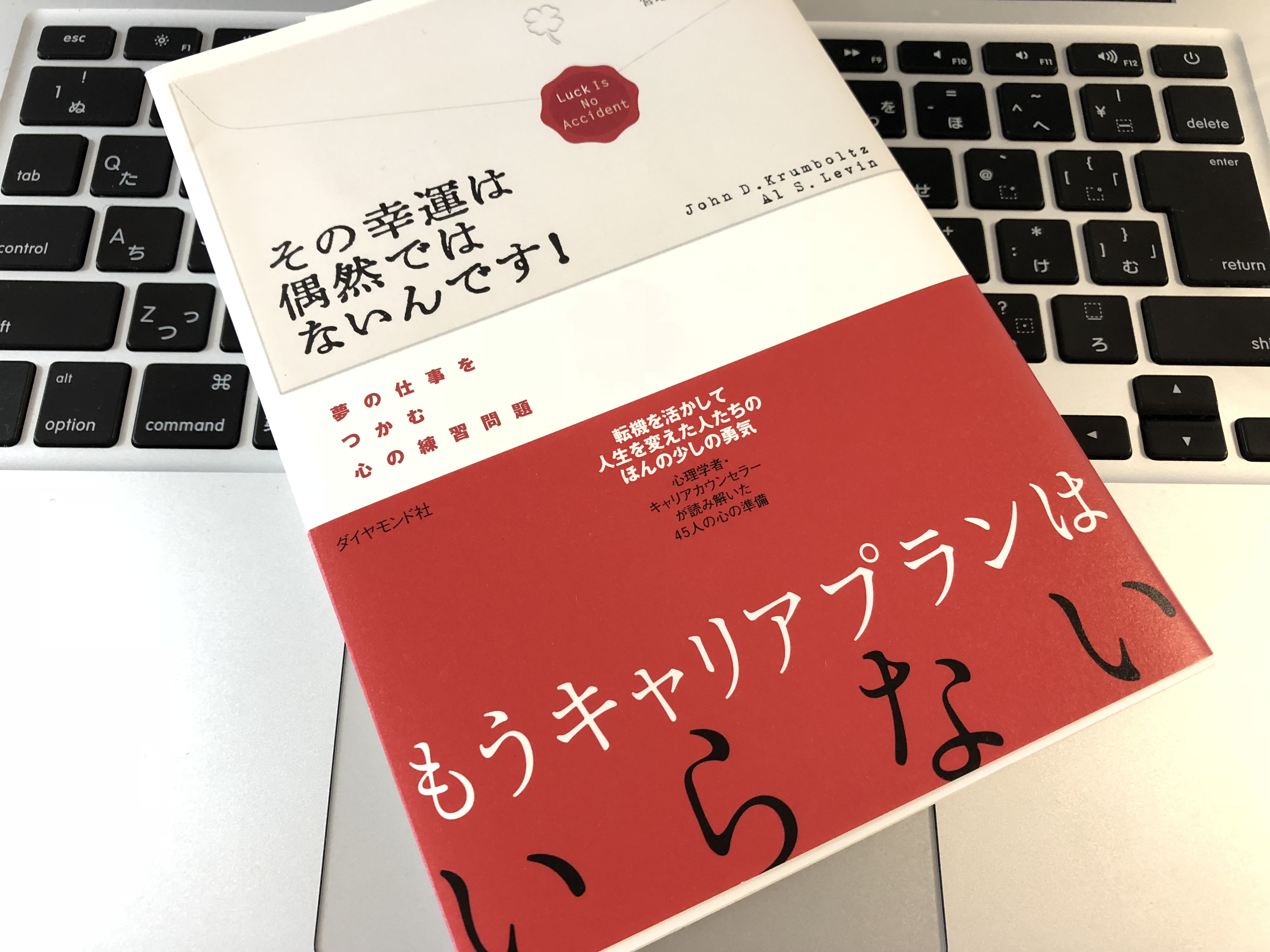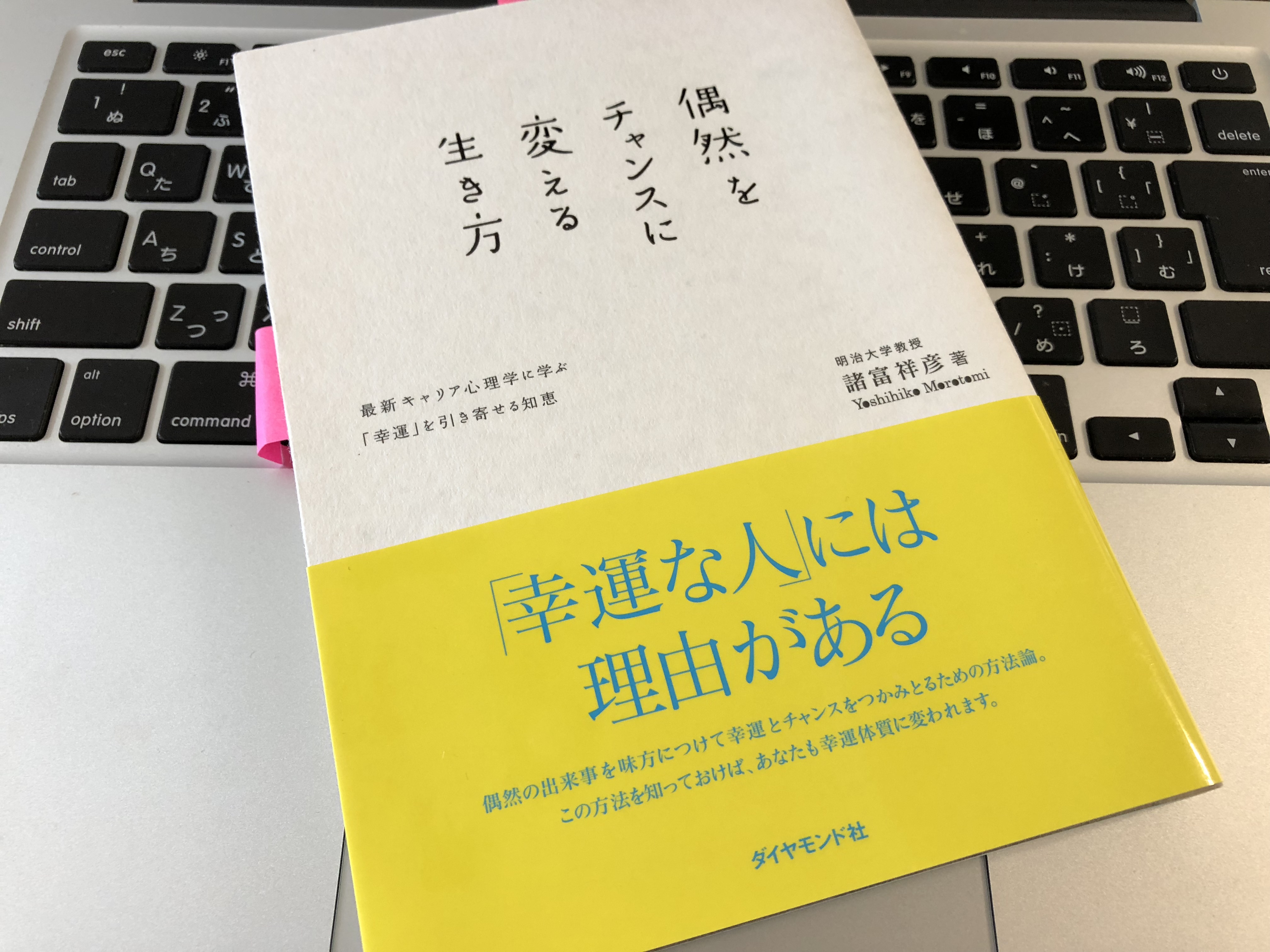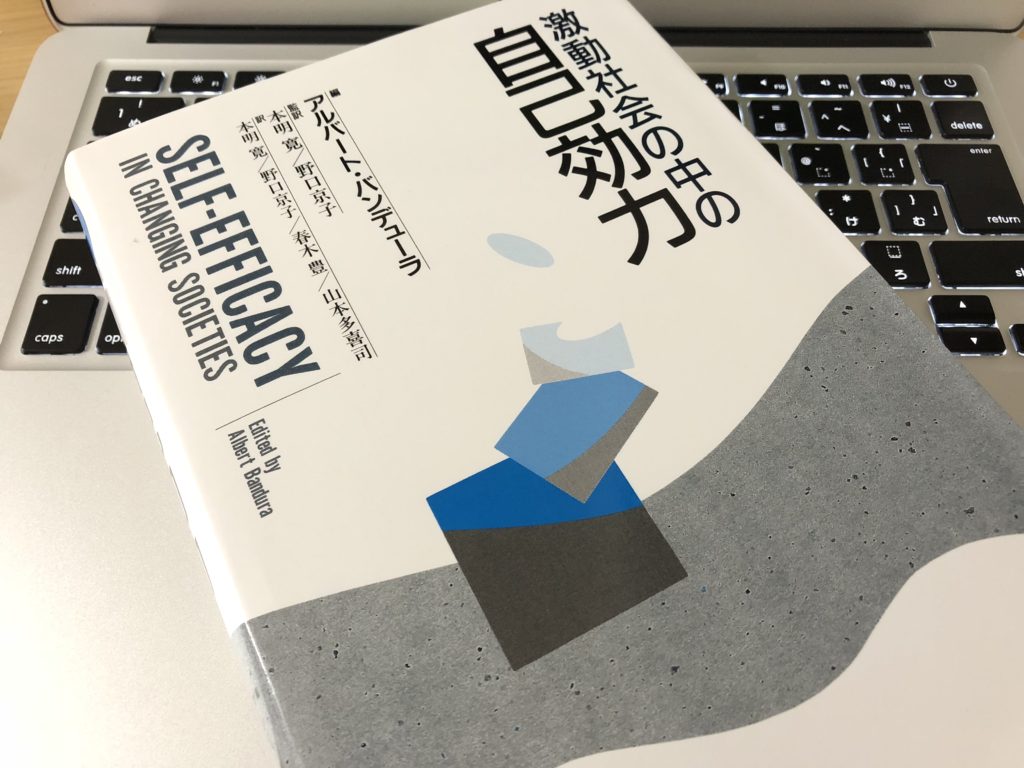Planned Happenstance 〜プランドハップンスタンスで築くセカンド(ネクスト)キャリア〜
計画的偶発性理論の実践
クランボルツ博士のキャリア論
「偶然の出来事は人のキャリアに大きな影響を及ぼし、かつ望ましいものである」

2010年に受講した日本マンパワーのキャリアカウンセラー養成講座。その時に使っていた"キャリアカウンセリングの理論"というテキストにある プランド・ハプンスタンス・セオリー(ハップンスタンスラーニングセオリー)を改めて学び直そうとしています。
プランドハップンスタンスセオリー(ハップンスタンスラーニングセオリー)を提唱されたクランボルツ博士は、スティーブ・ジョブズ氏がスピーチをしたことで有名なスタンフォード大学の名誉教授でもあり、私が所属するJCDA(日本キャリア開発協会)の名誉会員でもあられます。
※クランボルツ博士は2019年5月に他界されました。(全米キャリア開発協会 National Career Development Association:NCDA より発表)個人的には、この理論から多くの勇気をいただいたことに感謝しています。心よりご冥福をお祈りいたします。
良いキャリアの機会を獲得するための5つのスキル
人生で遭遇するさまざまな出来事。そのほとんどは自らが計画して起こしたことではなく、純粋に偶然と感じることから必然と感じられることまで、予期せぬ出来事が占めています。
その偶然の出来事を"自分にとって望ましいキャリアの機会"とするために私たちはどうあれば良いのでしょうか。
プランドハップンスタンスセオリーの5つのスキル「好奇心・持続性・柔軟性・楽観性・冒険心」を深めるために、ここで自分自身の経験をふりかえってみることにしました。
1.好奇心(新しい機会をつかもう)
「心が動いたら、行動してみる」
情報処理の講師として専門学校に勤めていた30代前半。職業経験のない学生さんや、再就職を目指すための職業訓練を受講されている生徒さんたちとともに過ごす日々。そこで段々と就職に関する相談を受けるようになりました。
相談されるたびに、どう対応してよいのか分からず自分にモヤモヤ。不甲斐なさから、職場(校内の就職課担当)の先生に相談してみることにしました。「生徒さんから就職の悩みを持ちかけられるけれど、どうしたら良いか分からなくて・・・。」と。
私の悩みを聞いてくださったのは、CDA(キャリアデベロップメントアドバイザー資格・現在は国家資格キャリアコンサルタント)1期生の先生でした。
「そんなに相談されるなら、あなたが勉強してみたら?」
先生は私にそうおっしゃいました。当時は貯金もなく、 専門実践教育訓練給付金もなく、教育訓練給付金制度は一時期80%あったものの40%(20%)に引き下げられていた時期。養成講座に通うために、およそ30万円を用意しなければなりません。どうやって払おうか?と悩みながらも他者の役に立ちたい一心で情報収集をし続け、学びへの気持ちを固めていきました。
ここまでを振り返れば
- 就職課の先生を頼って、相談しにいく
- 就職課の先生の勧めをもとに、情報収集をする
- 貯金はなかったけれど、簡単にあきらめない
自分がいました。そうこうしているうちに在住している県の制度として、若年者の就労支援を目的とした給付金が3年間限定で実施されると聞き、運良く該当していることが判明。県庁に申請に行ったときには「あなたが第1号よ!」と職員さんに笑顔を向けられたことは今でも良き思い出です。結果として費用負担が半分程度で済んだことは、本当に幸運だったとしか言いようがありません。
2.持続性(やりたい?やりたくない?)
「できるかできないかより、やりたいかやりたくないかを大切にしよう」
私は自分でもあきれるほど、他者からよく思われたい願望の強い人間です。嫌われたくない、笑われたくない、恥をかきたくない。社会適応とも言えるのかもしれませんが、いつしか思っていることを表現しないことが当たり前になっていました。
切迫早産で決めた退職も、もう少しゆっくり考えれば良かったのかもしれません。つわりもきつく、マイナス思考に陥るばかり。仕事が思うようにできない自分を見られるのがそれほど嫌だったのか、あのときは辞める一択しかありませんでした。
産後は、再就職のために一時保育を利用して何件も面接に行きましたが、マッチングする再就職先は見つからずじまい。やりたい仕事をやるにはフリーランスでやっていくしかないと思い腰を上げました。
「仕事がない?どうしよう。名ばかりフリーランスなんてかっこわるすぎる!」
決意はしたものの、当初は不安と見栄とで大混乱。ただ、キャリアカウンセラーとして仕事がしたい気持ちだけは自覚していました。潜在求人にもアタックしてガムシャラに仕事を求め、職業訓練校でキャリアデザインの授業やキャリアコンサルティングをさせてもらえることになり、一歩前進。ただし、通勤にかかる時間は往復3時間。朝イチで保育園に預け、お迎えもギリギリ。家事と育児と仕事の両立は思った以上に大変な上、力不足にもがく毎日。
ほかにも公共施設のカウンセリング業務を運良く請け負うことができましたが、相談を受け始めてから5分も経たないうちに相談者が離席されるなんてことも。
資格を取得して数年が経っているのに、できない自分ばかりが目について相当へこみます。落ち込み、逃げたくなる自分がちらつくたび
「これから、どうしたい?」
自問自答の繰り返しです。キャリアカウンセラーという仕事は自分には向いてないんじゃないか。こんなに肩を落としっぱなしでいいのだろうか。家事も育児も本当に大変だし、もうやめてしまおうか・・。
弱気になりながらも
「キャリアカウンセラーでいたい? or いたくない?」
と何度も自分に問いました。うまくいかない日々が続くと、本心にふたをしてしまうことがあると知っていたからです。
どうしたい?の問いに「だって、うまくできないし・・・」とつぶやく私。一度、弱気になってしまうと、できるかできないかの物差しが大きく立ちはだかります。
世の中にごまんとある仕事。収入を得るための仕事であれば、キャリアカウンセラーにこだわる必要はありません。多くの人に出会えて数多の話をお聴きでき、さまざまな喜怒哀楽に触れられるキャリアカウンセラーという仕事は、生きることの厳しさも楽しさも教えてくれました。正解のない仕事だからこそ魅力がある、失敗してもやり続けたい、その失敗を糧に、また新たな力を身につけて私の中の力の限りを注ぎたい!
そうやって向き合っているうちに、キャリアカウンセラーという職業は私にとって無くてはならないものになっていきました。
3.柔軟性(思い込みに気づく)
「オープンマインドで」
以前、障害者の福祉サービスとして運営している就労移行支援事業所(難病や障がいがある方々が一般企業での就労を目指して訓練する事業所)や障害者職業センターなどで、精神障がい者の就労支援やリワーク支援に携わっていたことがあります。それらの業務内容をキャリアカウンセラーや産業カウンセラー仲間に話す機会は少なくありません。そんな話の延長で、
「数年後には、精神障がい者の就労支援の仕事につきたいと思っています。そのために今の仕事に区切りをつけることができたら退職をして、そのあと大学に入学して精神保健福祉士の資格を取って、再就職しようと計画しています。」
と話してくださった方がありました。
詳しい内容は割愛しますが、過去の経験から精神障がい者の就労支援に就いて、他者のお役に立ちたいという想いがひしひしと伝わってくるお話でした。
私は精神保健福祉士は取得していません。就労移行支援事業所で勤務したときも、障害者職業センターの職場復帰(リワーク)支援の仕事についたときもキャリアカウンセラー資格のみで入職し、産業カウンセラーは自己研鑽として働きながら通学しました。
もしも「精神保健福祉士を取得しなければ、精神障がい者の就労支援に就くことができない。」と考えている人がいるならば、それは思い込みかもしれません。現実的には無資格でもチャンスがある業界ですし、産業カウンセラーやキャリアカウンセラーの資格を取得しているならなおさらのこと。
自分の考えや計画を持ちながらも、それに固執することなく他者に開示し、他者からのアイディア、アドバイス、考えなどにも心を開く「オープンマインド」であれば、自身の考えや行動が柔軟になり、その後の可能性が、ぐっと広がるわけです。
こうでなければならない、こうしなければならないという気持ちから力強いエネルギーが沸き出ることもあります。その思いを否定するものではありません。ただ、思い込みから自分を縛り付けていないか?という点検が、良い人生を拓くきっかけになるかもしれないと思うのです。
4.楽観性(何とかななるさ)
「資格取得と自己効力」
20年前、情報処理の講師として「初級システムアドミニストレーター(現:ITパスポート)」という国家資格の受験対策講座を担当していました。その上位資格である「基本情報技術者」の試験対策もやってほしいという学校側の期待に応えるため、働きながら資格学校に通い勉強することになりました。それなりに努力をするも1回目は不合格。2回目も不合格で、3回目にしてやっと合格できた経験があります。
実はこのとき、基本情報技術者試験に8回チャレンジされた60代の先生が職場にいらっしゃったのです。私はその先生が好きで、よくお話を聞いていたためか、「8回もあれば、私もなんとかなるな」という楽観性が育っていたかもしれません。
・・・と、ある経営者の方にお話したところ、「8回とか、3回とかは(程度が低すぎて)講師として話しちゃいけないよ。」と言われてしまいました。(笑い話です。)それもそのはず、講師という立場なら"みんな揃って1回で合格しよう!そのために学び合おう!"という心意気が重要ですもんね。
◆◆◆
社会的認知(学習)理論を基礎に展開されてきたクランボルツ博士。ここで、社会的認知学習理論つながりから、アルバート・バンデューラ博士の「自己効力理論」について考えてみます。
バンデューラ博士が説く自己効力(感)とは、「結果をうみだすために、適切な行動を遂行できるという確信の度合い」を意味します。目標や課題に向かって、「自分は何とかやれる」「自分なら何とか努力できる」と、どの程度考えて準備できるかということです。
私の場合、基本情報技術者という国家資格を3回受験し、やっと合格することができました。その背景には、8回目にして達成された他者の姿の観察が含まれていました。また3回かかったとはいえ、合格を手にしたという自分自身の達成体験によって強力な自己効力感を得た後に、キャリアカウンセラーの資格取得をすすめられ、他者からの説得や励ましを受けるという一連の出来事に背中を押されました。
"自分の持つ力を信じることほど主要な力強いものはない"
まさしくその通り!と納得感が高まったのは、キャリアコンサルティング技能士2級の合格でした。数年前にチャレンジしたことがあったのですが、橋にも棒にもかからずじまい。自分には力がないと思い込み、落ちた経験を無かったものと消し去って自己防衛していました。しかし、あるきっかけが与えられ再チャレンジせざるを得ない状況に。せっかく与えられた機会なのだから、とにかく自分の持つ力を信じようと様々な誘惑のチャンネルを絶って集中しました。
その甲斐あって、ついに合格。「私でも、やればできるんだ!」という幸福感に包まれたあの感じ。高揚感は忘れられません。(・・・といっても、だんだん忘れてしまうのでしょうけれど・・・笑)それでも、何度もチャレンジして合格できたという経験は、これからの私に良い影響を与えてくれるに違いありません。
5.冒険心(やらないリスクを考えよう)
「小さなステップで」
やろう、やりたい!と思うけれど、できない・・・というときは、それぞれのメリット・デメリットを比較してみたり、行動そのものを見直してみたりします。やろうと思っていることが大きすぎないか、もっと小さな(スモール)ステップ、すぐできる(クイック)ステップにするにはどうすればよいか?といったアイディア出し(ブレーンストーミング)です。
"人生を謳歌している人""幸運に恵まれている人"は、必ず行動しているように思うのです。実践家の方々からも「小さな種を巻き続けることができるかどうかが大切だ」と教わりました。小さくてもアクションを起こし続けること、その結果から学ぶことが大切なのだと。どこに芽が出るかは誰にもわからないし、行動することをやめてしまったら、ひとたびに何も生まれなくなってしまうから。
やってみたあとの最悪の結果や失敗した時のことばかりを考えると、やらない方がマシという結論に至るかもしれません。でも、やらない選択から生まれる最悪の結果は?
失敗を恐れて「何もしない」ということに、大きなリスクが隠されているかもしれない。
いつの日か死を迎える時、「あれもこれも、やってみればよかった。」と思うのか「あんなことや、こんなことを、やってみてよかった。」と思うのか。おおげさかもしれませんが、そう考えることで冒険心を奮い立たせることも少なからずあるのです。
え?それなら私がどんなことに挑戦したかって?(突然の押しつけでスミマセン(笑))私は現在、キャリアコンサルタント養成講座の講師をしています。そう、スモールステップを踏んで講師の採用試験にチャレンジしたのです。
- 自分で口に出して言ってみる
「私は、キャリアコンサルタント養成講座の講師になりたい(のかもしれない・・)」
本心に触れるのは、いつになく怖いものですね。 - 他者に自己開示してみる
「いつか、キャリアコンサルタント養成講座の講師になりたいなと思っているんです。・・・できないと思うけど。」
最後におヒレがつくのは、いたしかたありません。 - 忘れる
(これは過去の経験からの私なりの戦略なので省略します。) - 求人を見つけて応募する
indeedに登録していたキーワードが引っかかり、偶然にも求人を見つけ、二度の面接&模擬講義をパスして講師として採用していただきました。
正解を探す努力よりも、選択後の満足度を高める努力を
ここまで、プランドハップンスタンスセオリーの5つのスキルを私なりに辿ってきました。私は、多かれ少なかれ5つのスキルを発揮された場面や経験が誰にでもあると確信しています。「ない」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、話し出してみると「ある」と判明することが多いのも事実です。
クライエントの自己理解・仕事理解・環境理解・キャリアプラン・内省・目標設定・意思決定などのお手伝いがキャリアカウンセラーの仕事です。まさに私自身も「こうなりたい」「こうでありたい」という理想と現実とのギャップを受け止めながら、自分にとって必要な能力を磨く努力を惜しみません。
変化が激しく、先の見通しが立ちにくい時代。計画を立てることは道標になりますが、その通りに進むことのみをOKとし、思考や行動を制限しては、自分にとって本当に大切なことを見逃してしまうかもしれません。
また正解はどこかにあるものではなく、自分で考えて、決めて、行動することで、自分らしい正解に近づいていくもの。そういう意味では知恵を絞ってやってみることに価値があると信じています。
偶然を幸運に変える力を育もう
ここまで私の経験や思いを綴ってきました。こんなつたない文章など読んでくれる人はいない、たとえ読んでくださったとしても、つまらないと笑われてしまうだろう・・・と思うと、何もしないこと(書かないこと)を選びたくなりますが、そんな自分を受容しつつ、書くことを選びました。
改めてここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。
私は、プランドハップンスタンスの考え方が大好きです。同じようにプランドハップンスタンスに興味を持って、たまたまこのページにたどり着いて下さった方々がいたとすれば、私にとってそれほど嬉しいことはありません。
向こうからやってくる偶然と、自分から計画的に創り出す偶然。どちらにせよ、より多くの"必然"を感じられる人生でありますように。
「偶然の出来事は人のキャリアに大きな影響を及ぼし、かつ望ましいものである。」
偶然を起こすよう、意識をして行動を変えていくことで、私たちにとってより良いキャリアの機会に変えていくことができる。行動すれば、事実が判明する、事実が判明すれば、さらにより良くすることができるのです。
もしもあなたがキャリア理論を勉強されている方だったとすれば、ご自身の経験を5つのスキルで整理されてみると新たな発見があるかもしれませんね。そしてこの偶然から、どのような行動を起こされるのでしょうか?
その一歩を踏み出す宣言と、ここまで読んで下ったご感想をお寄せくださると、泣いて喜びます。
・・・と書いたところで、誰からも便りなど来ないだろうとも思ってしまうのが、私の認知のパターンです。ですが、送ってくださる方がいらっしゃって、それには、とても勇気をいただきました。心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
見知らぬ者同士であっても、つながりがりあえるなんて、なんて素敵な世界なんでしょう。これからも、幾度も躊躇はするでしょうけれど、みなさんと共に行動していきます!